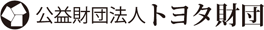ごあいさつ

新年度のご挨拶を申し上げます。昨2024年10月に、トヨタ財団は設立50年を無事に迎えることができました。これもひとえに常日頃から財団の活動を様々な形でご支援下さっている皆様方のおかげです。本当にありがとうございました。今年度は次の50年へと向けた第一歩を踏み出す大事な年で、年度初めにあたって決意を新たにしているところです。
トヨタ財団設立から現在に至るまでの50年を振り返ると、この間アメリカ合衆国とそのリーダーたちによる言動が、圧倒的な経済力と軍事力を背景として、よくも悪くも世界全体の動向に大きな影響を及ぼしてきたことにあらためて気づきます。卑近な例で恐縮ですが、私がそれを身近に感じた例を一つ紹介させてください。2012年春に私は東京大学の新任国際担当副学長として世界の大学幹部が集まる会議にはじめて出席しました。今振り返ると、グローバル化へ向かう流れの勢いが最も強かった時期です。この時に耳についたのは、アメリカの大学のリーダーたちが繰り返し唱えるdiversity(多様性)とmobility(流動性)という単語でした。国としての成り立ちがこの二つの価値を内包しているのですから、これを強調して国外からの研究者や留学生をより多く受け入れようとするのはアメリカの大学らしい主張だと思いました。会議ではイギリスやオーストラリア、シンガポールなど英語が日常語であり英語で教育を行っている国の大学がこの方向性を強く支持し、ほどなく日本を含む世界の多くの国の大学でもこの二つの価値の重要性が唱えられるようになりました。イギリスの会社がビジネスとして始めた大学ランキング(その大きな問題点は機会があれば別に論じます)の上位を独占しているアメリカやイギリスの大学を真似ようというわけです。
私も多様性と流動性という二つの価値は確かに大事だと思います。しかし、「多様性」と言いながら英語圏の大学では英語でしか研究教育が行われていません。言語の点ではとても画一的なのです。英語以外の言葉が日常的に使用されそれに基づく独自の文化環境を持つ非英語圏の大学とは初期設定が大きく異なります。大学の役割の一つが、その位置する国や地域におけるリーダーの育成と知の体系強化であるなら、非英語圏の大学が英語圏の大学の仕組みや構造をモデルとして単純にそのまま取り入れてもうまく行くはずがありません。当たり前のことですが、アメリカの大学の主張を鵜呑みにせず、またすべてを拒絶するのでもなく、その意味や内容をよく吟味し、自らにふさわしい針路を決めるべきです。
これは私の身の廻りの小さな事例ですが、もっと大きな局面でも同じことが言えそうです。例えば、昨今これまでとは打って変わって危機に瀕しているように見えるDEI(多様性=公平性=包摂性)という価値を取り上げて見ましょう。第二次トランプ政権は、アメリカ国内におけるDEI各種プログラムを廃止するだけではなく、長く途上国支援を担ってきたUSAID(合衆国国際開発庁)の事業の多くも打ち切りました。これをうけてDEI関連プログラムを縮小または撤廃するアメリカの民間企業も増えているようです。アメリカにはアメリカの事情があるのでしょう。しかし、このアメリカの国内情勢の変化は、今後世界各地に大きな影響を与え、DEIに懐疑的な動きが広がりそうな雲行きです。
DEIにつながる多様性や国際協力の重視は、現在のトヨタ財団の助成プログラムの方向性と重なり合います。では、アメリカの動向に合わせて、私たちはこれらをすぐに見直すべきなのでしょうか。私はそうは思いません。地球規模で取り組まねばならない多くの課題が見えるようになった現代において、地球上の様々に異なる環境で生きる人々がそれぞれの立場を認め合い相互につながって安定した人類社会というまとまりを作り上げることは、誰もが真剣に追求すべき重要な目標です。その際にDEIは欠かすことの出来ない大切な価値であるはずです。私たちは、この価値を大事にした各種活動を通じて、ぶれずに目標の実現を目指すべきだと思います。
アメリカの代表的な民間財団の多くは、伝統的に包摂などの理念や国際協力の実践を重んじてきました。現在の状況の下でも、これらの財団は粛々とそのような助成活動を展開していると聞きます。1兆円を超える財産を保有するマッカーサー財団は、政府が公的な途上国支援や国内への補助金をカットしたことに鑑み、今後2年間に亘り、年間の助成金総額を約600億円から約900億円に増額するとのことです。多様性や包摂、国際協力の意義は、アメリカでもまったく忘れられているわけではないのです。
トヨタ財団は、人類社会の確立という理念につながる広い意味でのDEIの実現に向けた国内外の動きに積極的に関わって行きたいと考えます。そのために、2025年度においては、わずかではありますが支援額の規模を拡大し、国際協力をはじめとする多彩な助成プログラムを展開します。また、国内外の関連組織や団体とのより緊密で効果的な連携の方法を探ります。これからの1年で何かが急に大きく変化するわけではありませんが、昨年秋の50周年記念シンポジウムや助成対象者の集いなどの機会に多くの方々から頂いた助言や激励、期待を糧にして、一歩ずつ着実に歩みを進めたいと思います。引き続き、皆様方の暖かなご指導とご鞭撻をお願いいたします。
2025年4月
公益財団法人 トヨタ財団
理事長 羽田 正